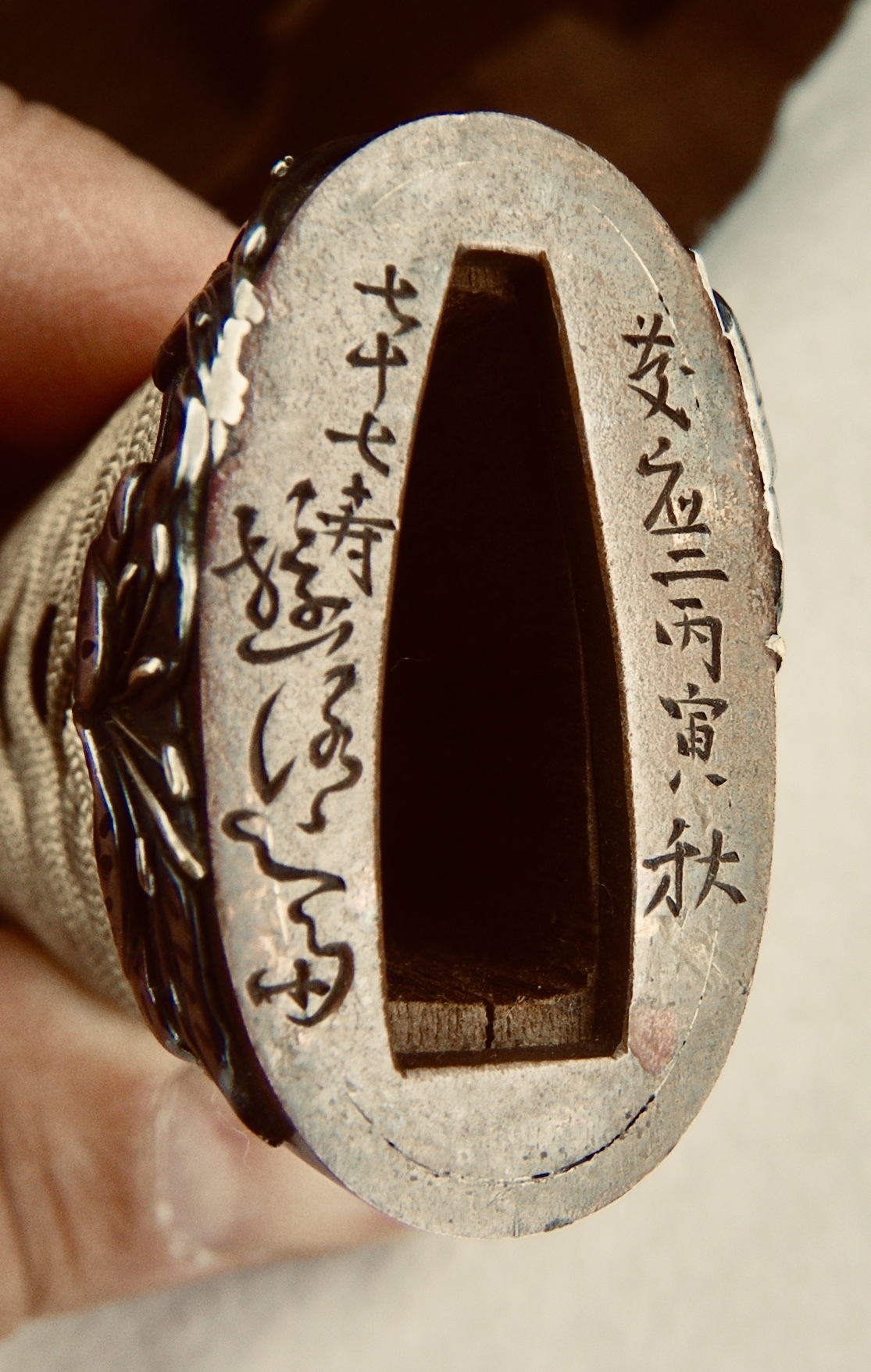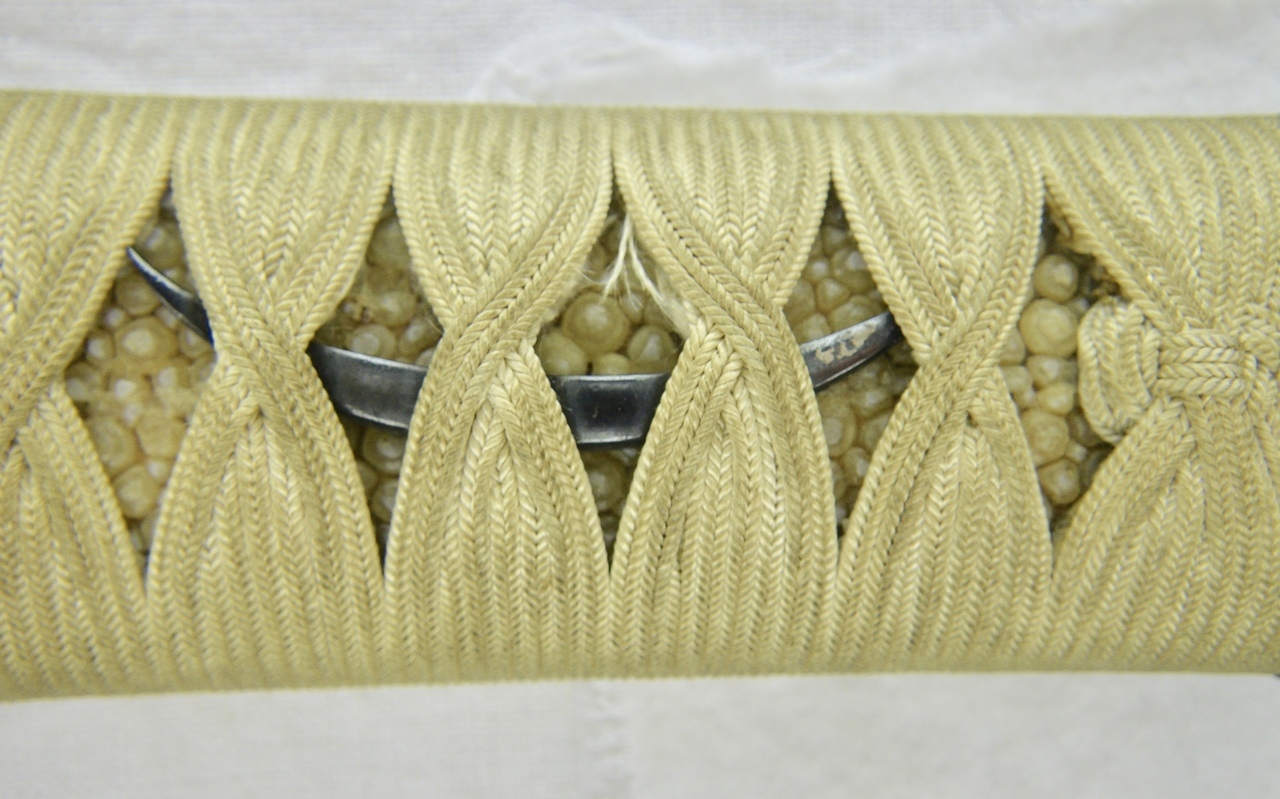令和2年4月17日 青貝微塵塗三分刻鞘脇差拵 遊洛斎赤文
青貝微塵塗三分刻鞘脇差拵 ご売約済
[揃金具]百合図 素銅地 据紋高彫 金銀赤銅色絵
縁銘=慶応二丙寅秋七十七寿遊洛斎
頭銘=(金象嵌銘)赤文
鐺銘=(金象嵌銘)赤文
鐔=鉄地 銘=成龍軒栄寿(金印)雨龍紋散
目貫=猿候補月図 表=猿図 素銅地金色絵
裏=月図 銀地
鯉口、裏瓦、栗形、鐺は素銅地彫込象嵌金銀色絵。
小柄=無銘 糸瓜図 素銅地 据紋象嵌。
柄=白鮫皮着芥子蛇腹糸組上巻。
桂野赤文は寛政元年(1789年)桂雲軒定治の次男として生ま
れた。兄は鷺州、弟南山と称し共に金工家であり金工一家であっ
た。赤文は青年の頃に京都に入洛し、それを記念に自分の号を生
涯「遊洛斎」とした。酒井家のお抱え金工師となる前に江戸にも
遊学し、この頃儒者であった亀田鵬斎に学び多大なる影響を受け
たようである。鵬斎は豪放磊落な人物で化政期に文人サロンにて
風雅な遊びを谷文晁、大田南畝、曲亭馬琴、山東京伝、酒井抱
らと一緒に楽しんでいた。また、酒に浸っては書をものしたとい
う粋人で「みみず書き」の書で親しまれていた。このみみず書き
に惚れたのが赤文であった。江戸遊学後、赤文は独特のみみず書
きで銘を彫り始めている事でいかに鵬斎から影響を受けたか窺い
知れよう。鵬斎自身は越後に良寛和尚を訪ね意気投合してから字
がグニャグニャくねりだしたらしく、歴史の深みを感じずには
いられない。赤文は体が大きく髭を蓄え、風体異風で飄々とし
ていて「みみず書き」を地で行くような人であったようである。
この拵を眺めてみると、独特の雰囲気を醸し出していて個性的
でもある。特に縁頭の百合の迫力には圧倒されてしまう。当時貴
重な赤味の強い緋色銅(ひいろどう)を使い独特の造形美に仕上げ
ており、赤文ならではの作品であろう。また目貫も名工「安親」
風であり深みのある作品に仕上がっていて,つい少欲知足の言葉
を思い浮かべてしまう。水に浮かぶ月を取ろうとして溺れ死んで
しまう猿猴捕月のお話しである。赤文は金銭に執着せず、信仰心
厚く、また人情に厚い人柄であったようなので喜寿になるにあた
り、自らを戒めるためにこの目貫を使ったのではないだろうか。
鵬斎から学んだ人をくったような書きぶりの銘を生涯刀装具に切
り続けた粋人であった。
保存刀装具鑑定書
写真をクリックすると拡大されます。
お問合せ・ご相談
担当:柴田和光
親子三代、信用第一に美術刀剣の商いをして参りました。日本刀は日本にしかない芸術品であり、文化であります。
お客様のご希望をお聞きしながら、御刀、刀装具をご紹介できればと思っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。お客様のご来店を心からお待ちしております。
柴田 和光